記号的身体と「質感」
前回はキャラクターの記号性について図像の面から検討したが、この議論は図像以外の要素にも適用できるのだろうか。例えばアニメキャラは声(音声)も持っているが、これは現実世界と遜色ない情報量を有している様に思われる。それでもアニメキャラの身体は記号的なのだろうか。
音声と質感
ここでまず前田愛『増補 文学テクスト入門』(筑摩書房、1993)の村上春樹『風の歌を聴け』について述べる部分を引用しよう。
ディスクジョッキーが登場する場面には、「オン」と「オフ」という記号が予め書かれています。(……)聴き手としては、ディスクジョッキーの語りがそこに現前している。しかし、ディスクジョッキーの語りを聴いている聴取者は、そこで彼の顔、表情を思い浮かべるということはしないだろうと思う。つまり純粋に切り離された言葉だけが並べられている。ところが、オフのスイッチが入ったところでディスクジョッキーがでたらめなおしゃべりをする。あるいはしゃっくりが出てくる。ここのところでは、まさにディスクジョッキーの身体性、あるいは内面というものがわずかに露出している。
(p.34-35)
VTuber(に限らず配信者全般?)の配信を結構見ている人間であれば、この「オン/オフ」についてピンと来るところがあると思う。離席時にミュートされなかったマイクから伝わる生活音、通話やツイキャス(スマホで楽に配信する為のプラットフォームとして使われる事が多い)での音質が悪く距離の近い声、そういったものに感じる「質感」こそ、ディスクジョッキーの「オフ」において表現されている音声の豊かな情報量だろう。それは発話内容だけを意味内容とする純粋な言葉ではなく、意図せずに生じた発話者に関する情報をも含んでいる。
逆に言えば「オン」の時の音声には、「現実の身体」を窺わせる要素が注意深く除去されている。そこに含まれる言葉通りの意味以上のものは、強調による注意の提示だとか、声色による単純な喜怒哀楽の伝達だとか、そういった心理的情報だ(パラ言語情報・非言語情報と呼ばれる)。発話者の体調だとか、録音環境、エンコードによる劣化、そうしたメッセージたり得ない情報は極力削るべきものとされる。(そうした「質感」に注目する鑑賞態度はありうるが、少なくとも公に語るべきものとは見做されない。)
こうして考えると、実のところアニメキャラの音声は記号的身体に調和する様に強い制約を受けている事が分かる。
動きの記号化、リアルな記号
同様な事態はアニメキャラの動きについても言える。キャラクターはその記号的身体の情報量に見合った簡潔な動きが期待されており、息遣いだとか瞬きだとかの些細な動作ははっきりとした意図無くして描かれる事がない。
ディズニーの様なアニメーションでは動きがより自然主義的に、現実で動くものは全てその様に動かして描かれる。こうしたフルアニメーション(基本的に秒間24フレーム全てかその半分を動かす)に対し、動いて見せる為に必要な分だけ動画枚数を使えばよいというリミテッドアニメーション(元々は20世紀美術が写実主義を克服したのと似た美学的追求だった様だが)を先鋭化させ、自身の記号体系を導入してストーリーのメディアへ変貌させたのが手塚治虫だ。この日本型リミテッドアニメーションの系譜にあるのが現在の(オタク的、萌え系)アニメであり、画面上での動くもの・動かないものの対立は色濃く受け継がれていると言えるだろう。一方その枠組みの中でも現実世界に基づくリアリズムへの志向は確かに存在し、特に戦闘などの場面では体重の乗った踏み込みだとか慣性を反映した武器の扱いだとかが視聴者から「リアル」と評価される。ただそれも必ずしも現実の動きに即している訳ではなく、受け手が重量感などを読み取れる様に誇張している面があり、やはり写実的な描写のみならず記号的な作用を通じて、現実の身体を提示する事を志向している部分がある。
アニメ『この素晴らしい世界に祝福を!』(2016)は特にリミテッド的な作画をギャグアニメとしての雰囲気の形成に活かした作品だが、第5話では主人公カズマの非常に滑らかな手の動きを描いている場面がある。
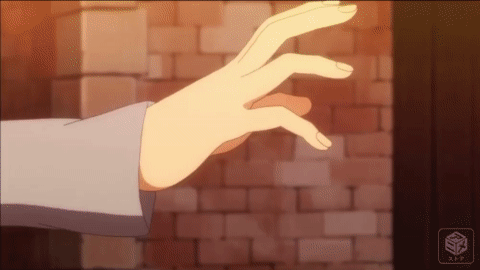
GIF化によりフレームレートが下がっているが、手の動きの際立ちは十分に確認できるだろう。特に逃げ出す直前の女性キャラクター達の顔の震えが僅か2枚の絵の反復で表現されているのと対比的。
「ぬるぬる」動く手によっていやらしさを表現している訳だが、記号論の観点から言えばその動きによって現実の身体(手)を表象し、更にその手がリアルな人間の欲望を示唆している(共示している)と分析できる。現実の身体としての手は実際そこにあるというよりも、単にカズマの記号的身体の一部となって演出に寄与しているに過ぎない。言語表現での比喩、「もののたとえ」に当たるものと言えるだろう。
動いてはいないが、より極端には『化物語』(2009)での実写映像の挿入が思い出される。(これは尾石達也氏の演出によるものらしい。)


左:サブリミナル的に挿入される実写カット、右:同キャラクター(羽川翼)の通常の描写
心象描写においてキャラクターが実写映像により提示される場合、別にそのキャラがそうした外見をしているという事ではなく、そこで表現される感情の切実さ、生々しさを伝える為の記号としてのみ働いている。尤も『化物語』での実写映像はやや無造作に用いられているからこうした読みはあまり有効でないかもしれないが、とにかく(同作でこれも度々挿入される、正に手塚治虫的な漫画表現と同じ)写実性・類似性が薄れたコード的な図像である事は確かだろう。
動きの場合に興味深いのは、いくら情報量やノイズが多くなったとしても実写ほどの違和感を与える事はない点だ。これはあるいは我々の物の識別が静止像に大きく依存している所為なのかもしれない。
概念としての身体
こうして分析すると、先の記事において概念としてのキャラクターを一括りにせず「記号的身体」を置いた事の意義が見えてくるのではないかと思う。
キャラクターの身体は単なる図像のパターンではなく、それ自体一つの概念なのである。そして概念である以上、図像に限らず様々な表現による提示が可能であって、「まんが・アニメ的」という言い方ではその存在性を捉える事はできない。ライトノベルであれ、ドラマCDであれ、やはりそこにはキャラクターの記号的身体が提示されているのであって、我々は全メディア(全-感覚モダリティ)的な概念記号の体系によってキャラクターを読み解いているのである。
「質感」とは言わばその記号体系では解釈できない剰余の部分だが、これによりキャラクターは活き活きとした印象を見せたり、あるいはキャラクターに収まらぬ生々しさを見せたりする。ここでキャラクターの内面は連続的に限りなく「人格」へ近づけるにも拘わらず、記号的身体は「不気味の谷」の如き(あるいはそれ自体か?)断絶によって生命感の追求を圧し留められているかの様だ。
キャラ(キャラクター)の話というと文化論系の方向に行く事が多い様に思われるのだが、こうした基礎的なキャラクター認知の特性こそ私が「キャラクター論」で追究したい領域である。